春休みのメイン教材として取り組んでいる《塾技100・厳選20単元》。
この問題集のおかげで、娘の“得意・不得意”がはっきり見えてきました。
特に浮き彫りになったのが…
理解が追いつかない…娘の苦手単元たち
「場合の数」は、樹形図からつまずいている!
出た!中学受験の定番「場合の数」。
この単元、想像以上に手強い…。
「どうやって数えていくの?」
「抜け漏れはない?」
「順番が関係あるのかないのか…?」
とにかく、樹形図の書き方そのものから、娘にはピンと来ていない様子です。
「1つ選んで、次に2つ目を選んで…」と話しても、
「あれ?今何通り目?」と混乱…。
何度か一緒に書いて見せましたが、今のところ「理解」には届かず。
本人も「難しい〜!何が分からないのかも分からない…」状態でした。
「食塩水」は、“同じ濃度”の概念がつかめない
もう1つの苦戦ポイントは「食塩水の問題」。
特に、「ある濃度の食塩水から少し取り出したとき、それも同じ濃度」という部分がピンと来ないようです。
「取り出したら塩の量も水の量も減るよね?」
「なのに濃度は同じなの?なぜ?」
この疑問をうまく整理できず、“感覚的に理解できない”から解けない、そんな壁にぶつかっています。
一度理解できればぐっと進むのですが、今はその“ひらめきの瞬間”にまだ届いていない感じです。
苦手と向き合うことは大切。でも…
正直なところ、親の私も焦りはあります。
「合不合判定テストまであと数日なのに…」
「こんなに苦手だと点数に影響するよね…」
でも、娘は今まさに頑張っている真っ最中。
できない問題に直面しても、投げ出さずに「もう一度やってみる」とプリントに向かっています。
この姿勢だけでも、大きな成長!
今は“できるようになる前段階”
「苦手単元が分かった」=「今後の学習の方針が立てられる」ということ。
この春は、その“洗い出し”ができただけでも大きな一歩です。
今後の方針としては…
- 場合の数は、まずは樹形図のルールを反復練習
- 食塩水は、てんびん図や面積図を併用しながら理解をサポート
- 1回で理解できなくても、5回、10回と繰り返して“慣れ”を作る
このスタンスで、娘のペースに寄り添いながら一緒に頑張っていきたいと思います。
合不合判定テストまであと少し
できない問題に目が行きがちですが、実は「前まで解けなかった問題が今は解けるようになっている」ものも確実に増えてきています。
焦りすぎず、でも1日1日を無駄にせず。
今は、娘と一緒にラストまで「やりきること」を目標にしています。
苦手単元も、いずれは“得意”になるかもしれない。
そんな日を夢見て、明日もまたがんばります!

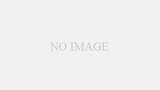
コメント