合不合の結果は「偏差値50」
春休みにしっかり対策して臨んだ合不合判定テスト。
結果はというと…算数の偏差値は50でした。
目標としていた「偏差値60」には届かず、正直ちょっと悔しい気持ちです。
春休みは塾技100の厳選20単元に集中!
春期講習は受講せず、我が家では市販教材『塾技100』の厳選20単元を繰り返し取り組みました。
使用した単元は次の通りです:
001 計算の工夫 / 002 逆算 / 006 過不足算 / 007 つるかめ算①
008 つるかめ算② / 010 仕事算 / 013 平均算 / 014 相当算
015 割合の表し方 / 017 食塩水① / 018 食塩水② / 021 旅人算②
022 ダイヤグラム / 024 通過算 / 025 流水算 / 026 図形上の点の運動
027 角度① / 030 三角形・四角形 / 069 平行と合同 / 098 場合の数
これらの単元は過去のテストでも頻出だったものや、苦手意識の強いテーマを中心に選んでいます。
結果が振るわなかった理由は…
振り返ってみると、塾技100の難易度が高すぎたのかもしれません。
標準〜発展レベルの問題が多く、1回で理解できないこともたくさん。
中には3回やっても、娘が「わからない…」と手が止まる問題もありました。
最終的に、「解けない問題」を解けるまでに持っていくことができなかったのが、
偏差値60に届かなかった最大の理由かなと感じています。
基礎を軽視してしまったかも…
今思えば、塾技100に取り組む前に、もっと基礎を丁寧に復習しておくべきだったかもしれません。
「何度もやればできるようになるはず」と信じて繰り返してはいましたが、
そもそも基礎が理解できていなければ、解法の意味もピンときません。
“難問対策”に重きを置きすぎて、
“基礎固め”がおろそかになってしまった感は否めません。
今後の課題と方針
今回の合不合での経験を通じて感じたのは、
- 理解が追いつかない単元は基礎に戻る勇気を持つこと
- 繰り返しの中でも「なぜできないのか」を分析すること
- ただ“回数をこなす”のではなく、“解けるようにすること”にフォーカスすること
この3つがとても大事だということ。
次の模試に向けては、
塾技100の難単元は一旦保留にして、予習シリーズや原田式プリントなどを使って基礎に立ち返る予定です。
まとめ|成果が出ない時こそ、やり方を見直すチャンス
「やったのに結果が出なかった」ときほど、
落ち込むよりも「何を変えたら良くなるか」を考えるチャンスだと思っています。
娘は、模試後も前向きで、「もっと分かるようになりたい」と話してくれました。
その気持ちを大切にしながら、次へつなげていけたらと思っています。
また、進捗や工夫はこのブログで綴っていきますので、同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです!

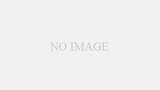
コメント