今回の週テスト、結果は偏差値51
新6年生になって数回目の週テスト。
今回の算数の偏差値は**「51」**でした。
平均点よりは上。でも目指しているレベルには届いていない――
そんな、“惜しい”結果だったなと感じています。
答案をじっくり分析してみたら…
娘が頑張って受けたテスト、結果が出た後が本番!
…ということで、さっそく一緒に答案をじっくり分析してみました。
間違えた問題は全部で5問。その内訳はというと…
- 前回の週テストの範囲だった問題:2問
- 今回の新出単元「場合の数」の問題:2問(正答率30%以下)
- 基本問題:1問
正答率30%以下の問題は“仕方ない”けど…
「場合の数」はそもそも苦手な単元。
さらに、正答率30%以下と聞けば、“解けなくても仕方ない”問題とも言えます。
ここに関しては、引き続き基礎からじっくり取り組んでいくしかないですね。
実はすでに、場合の数に特化したやさしい問題集を導入して練習中です。
問題は、“本来は解けたはず”の3問
それよりも悔やまれるのが、
- 前回のテスト範囲の復習不足からの失点が2問
- 問題文をよく読んでいれば解けた基本問題が1問
この3問です。
もったいなすぎる失点の内容
特に残念だったのが、「正方形」の問題。
問題文にははっきりと『正方形』と記載されていたのに、
その部分を読み飛ばしてしまい、辺の長さを出せなかったのです。
つまり、
**“条件を読み飛ばして、正しく解けなかった”**という“うっかりミス”。
でもこれは、「ただのケアレスミス」では済ませられない問題でもあります。
ケアレスミスは、実力のうち?
よく言われる「ケアレスミスも実力のうち」。
まさに今回は、それを実感させられた内容でした。
読み飛ばしを防ぐには、本人が意識的に「読む力」を育てるしかない。
親がそばで「ちゃんと読みなさい」と声をかけても、
テスト本番では自分で自分を律するしかないんですよね…。
改善策を考えてみた
とはいえ、ただ「気をつけなさい」では改善しません。
今回の反省を活かして、娘とこんな取り組みをしてみることにしました。
●「問題文チェックリスト」を作る
問題を解く前に…
- 図形の条件はすべて読み取ったか?
- 数値の単位(cm、mなど)は確認したか?
- 問題の“聞かれていること”は明確か?
…などを自分でチェックできるように、簡単なリストを作ることにしました。
●「読み飛ばし防止」音読も活用
家庭学習では、「黙読」ではなく音読で問題を読むようにすると
“読み飛ばし”が激減するという研究結果もあるそうです。
娘にも試してみたところ、
意外と真剣に読めてる!という発見がありました。
今後に向けて
今回のテストを通して見えたことは、
- 苦手単元はやはり基本から繰り返すことが大切
- 復習不足は確実に点数を落とす原因になる
- “よく読めば解けた”問題を落とさない意識が超重要!
算数は「考える力」だけでなく「読む力」も試される教科。
娘にも、問題文を丁寧に読むクセを、これからしっかりとつけさせたいと思います。
次回の週テストでは、**「読めば解けた問題はしっかり解く!」**を合言葉に頑張っていきます!

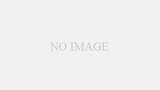
コメント